「親が亡くなったら、実家って誰が相続するの?」「自分は実家に住んでいるけど…兄弟とどう分ければいいの?」
そんな悩みを抱えている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
実家の相続は、お金の問題だけでなく、家族関係にも深く関わる繊細なテーマです。
特に兄弟姉妹間で話し合いがうまくいかないと、“争続(そうぞく)”に発展するリスクも…。
実家を相続する権利があるのは誰?
親(被相続人)が亡くなった場合、法律上の相続人(=法定相続人)になる人は、一定の順番と条件によって決まっています。
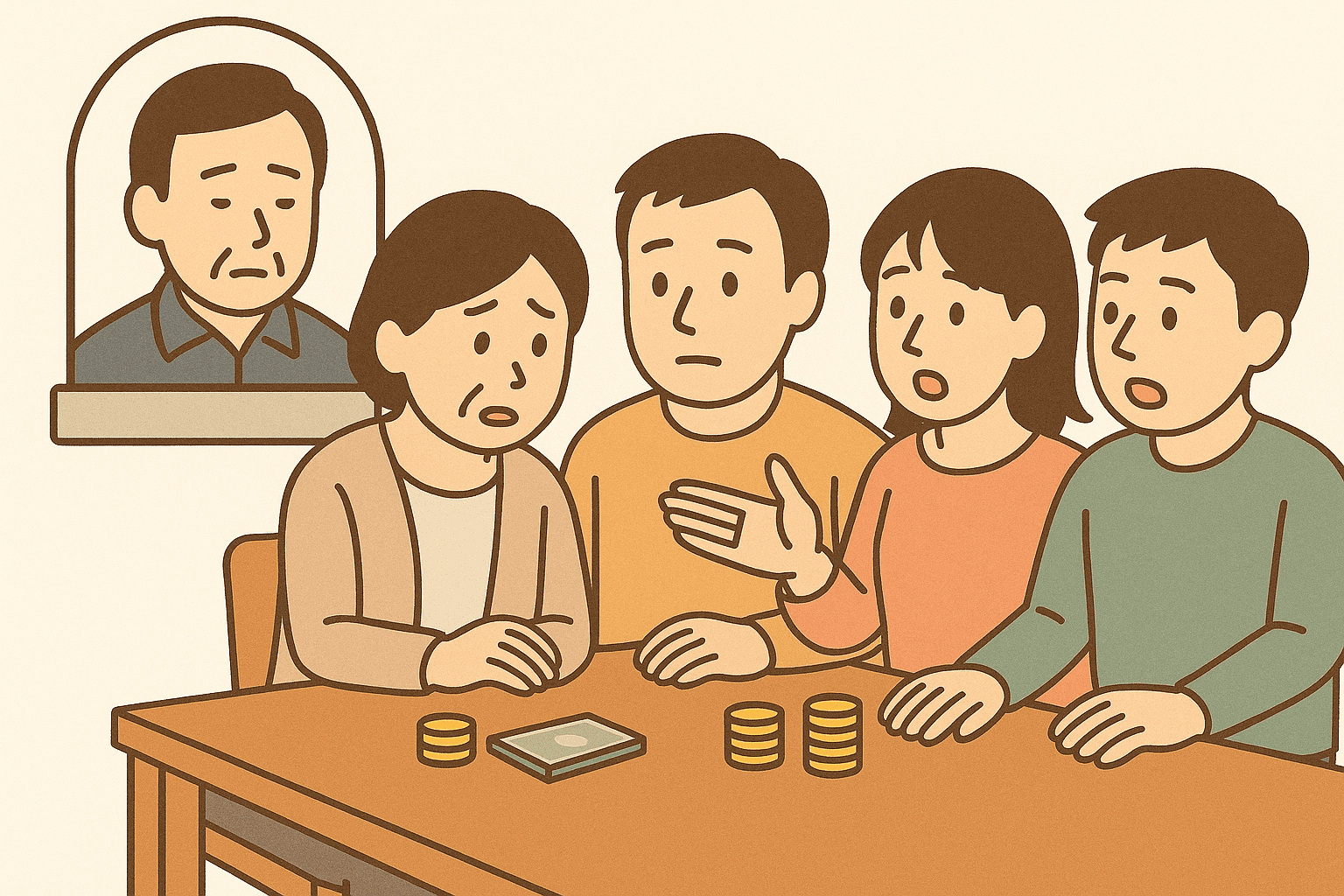
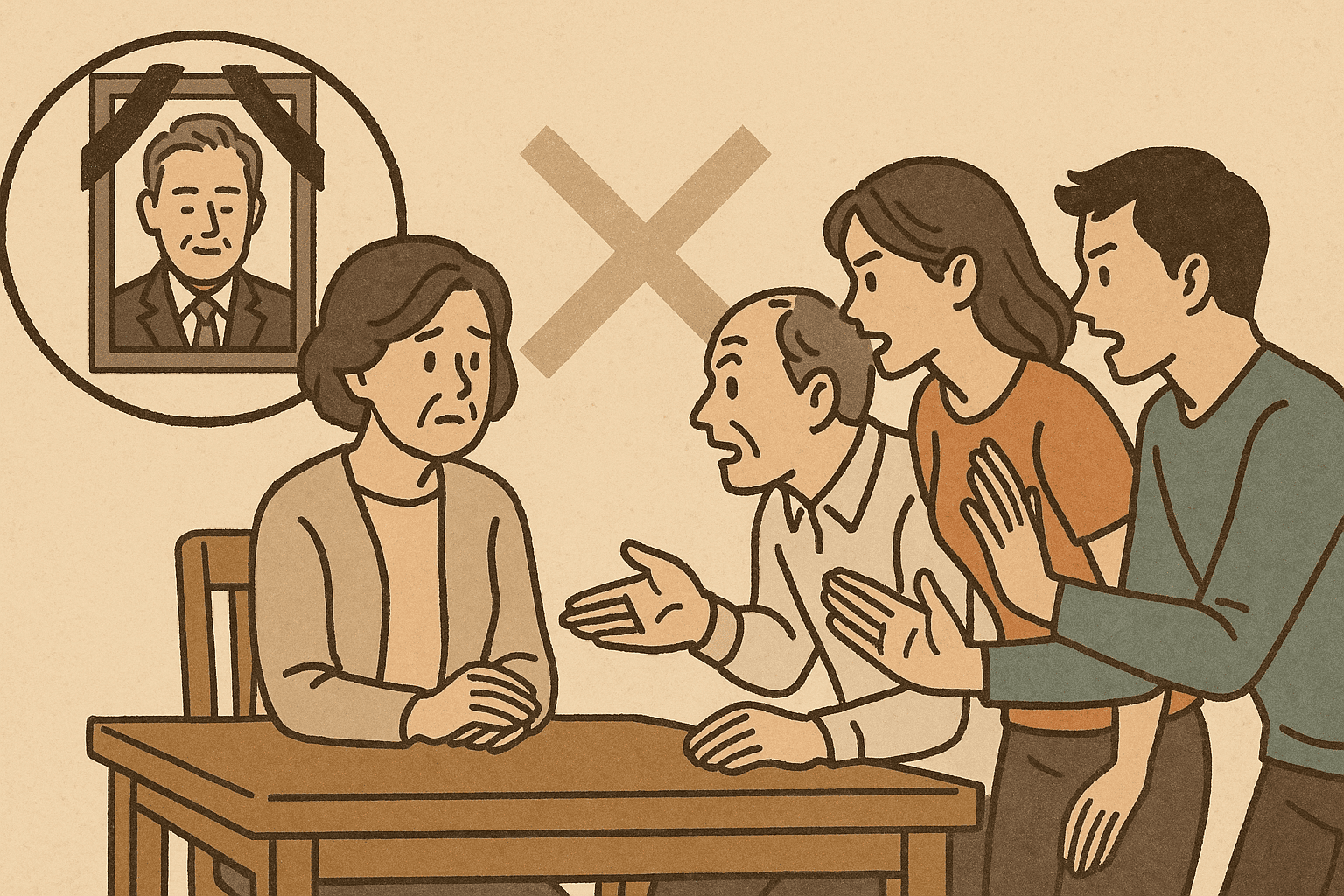
| 被相続人との関係 | 相続できるかどうか | 備考 |
|---|---|---|
| 子ども(実子・養子) | ◎ | 法定相続人として常に相続権あり |
| 配偶者 | ◎ | 法定相続人として常に相続権あり |
| 姪・甥 | △ | 原則不可。代襲相続の場合のみ例外で相続権あり |
| 叔父・叔母 | × | 法定相続人ではない |
| 血縁のない人(内縁・嫁など) | × | 相続人にはなれないが、特別寄与料は請求できる可能性あり |
▶︎画面を横にスワイプすると表を見れます▶︎
よくある相続トラブルとその対策3選
相続は「法律だけでは割り切れない感情」が絡むため、話し合いがうまくいかずにトラブルへ発展してしまうことも少なくありません。
特に実家の相続では、誰が住むか・誰がどれだけ被相続人に貢献してきたか・不動産の価値をどうみるか…など、考え方の違いが表面化しやすくなります。
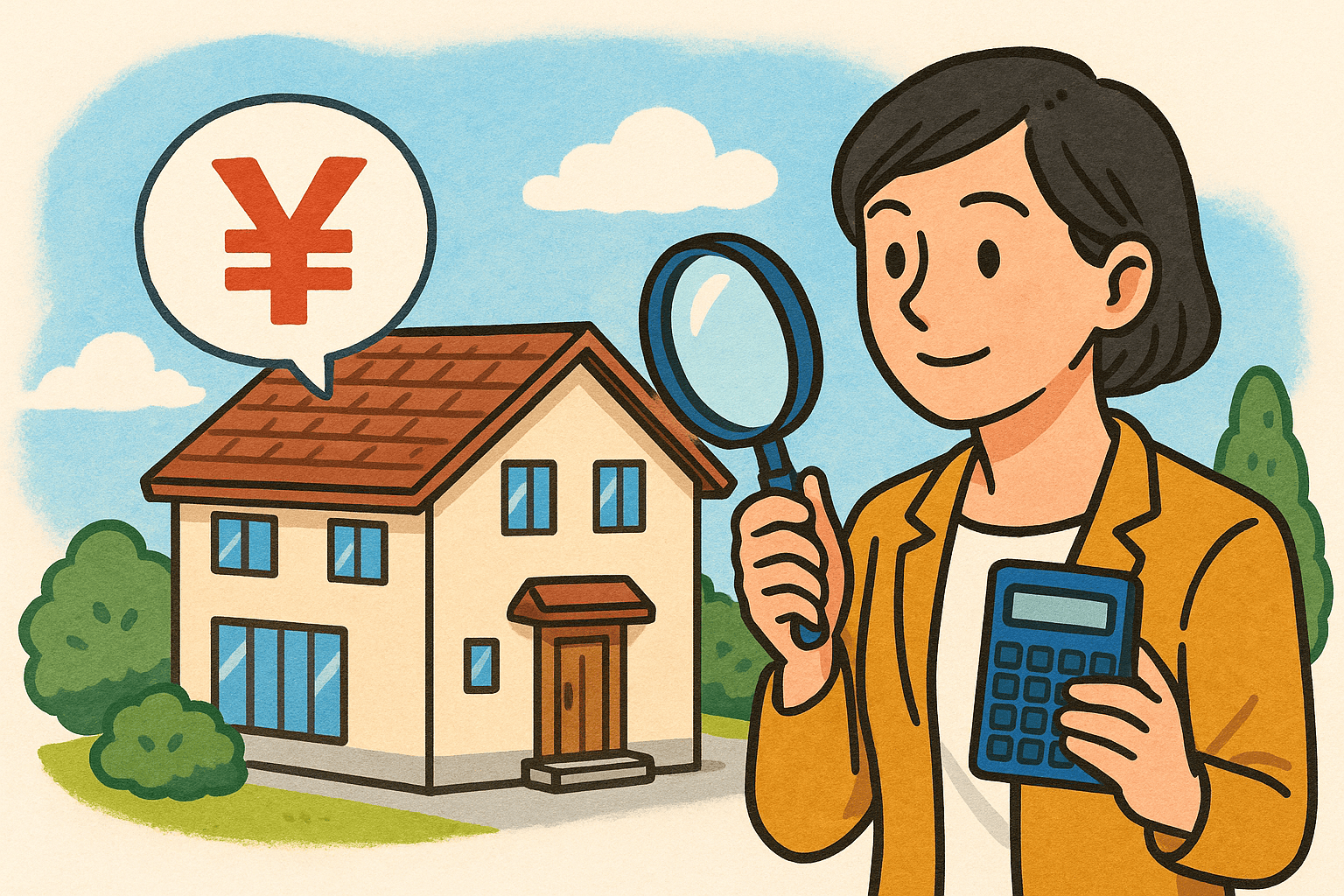
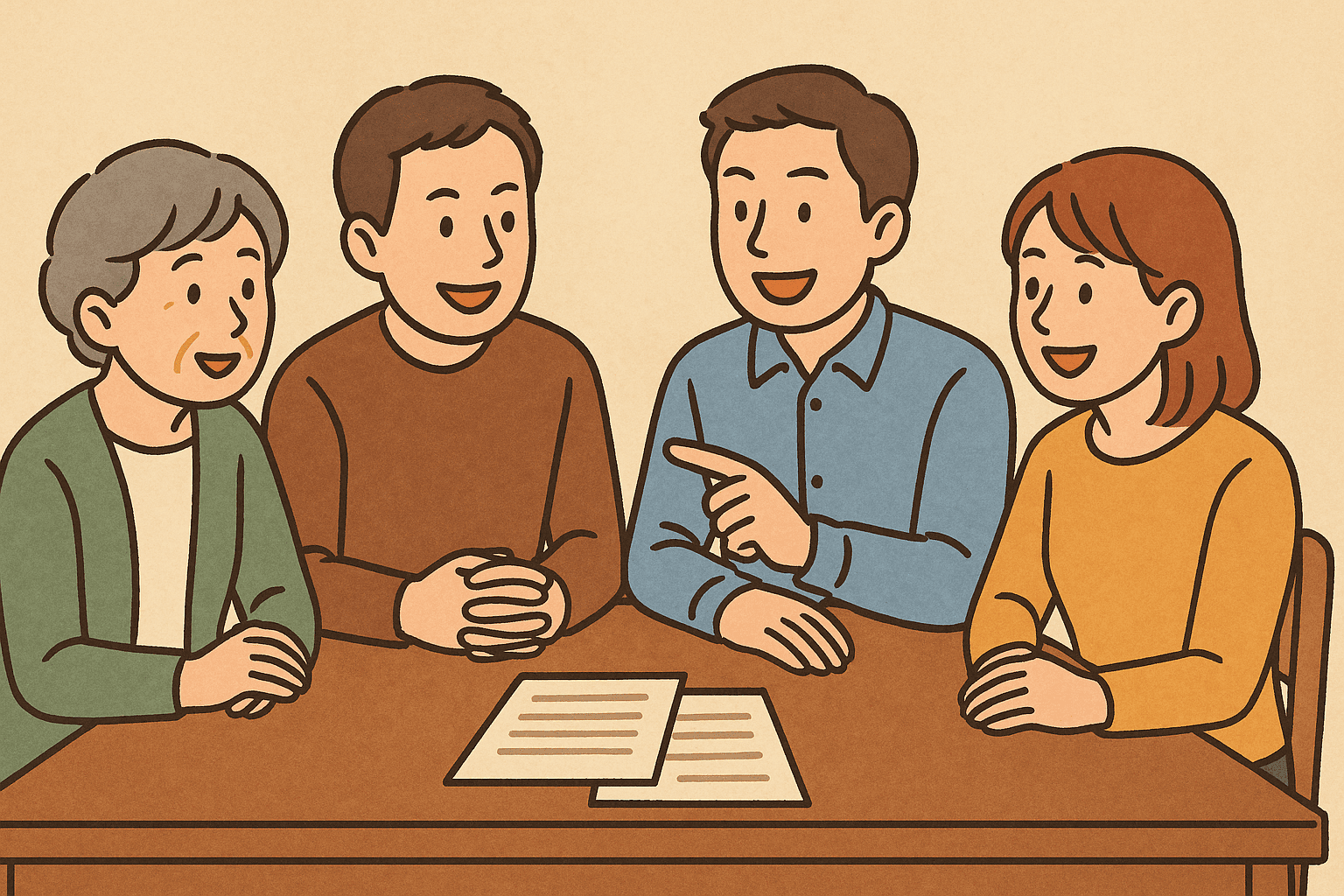
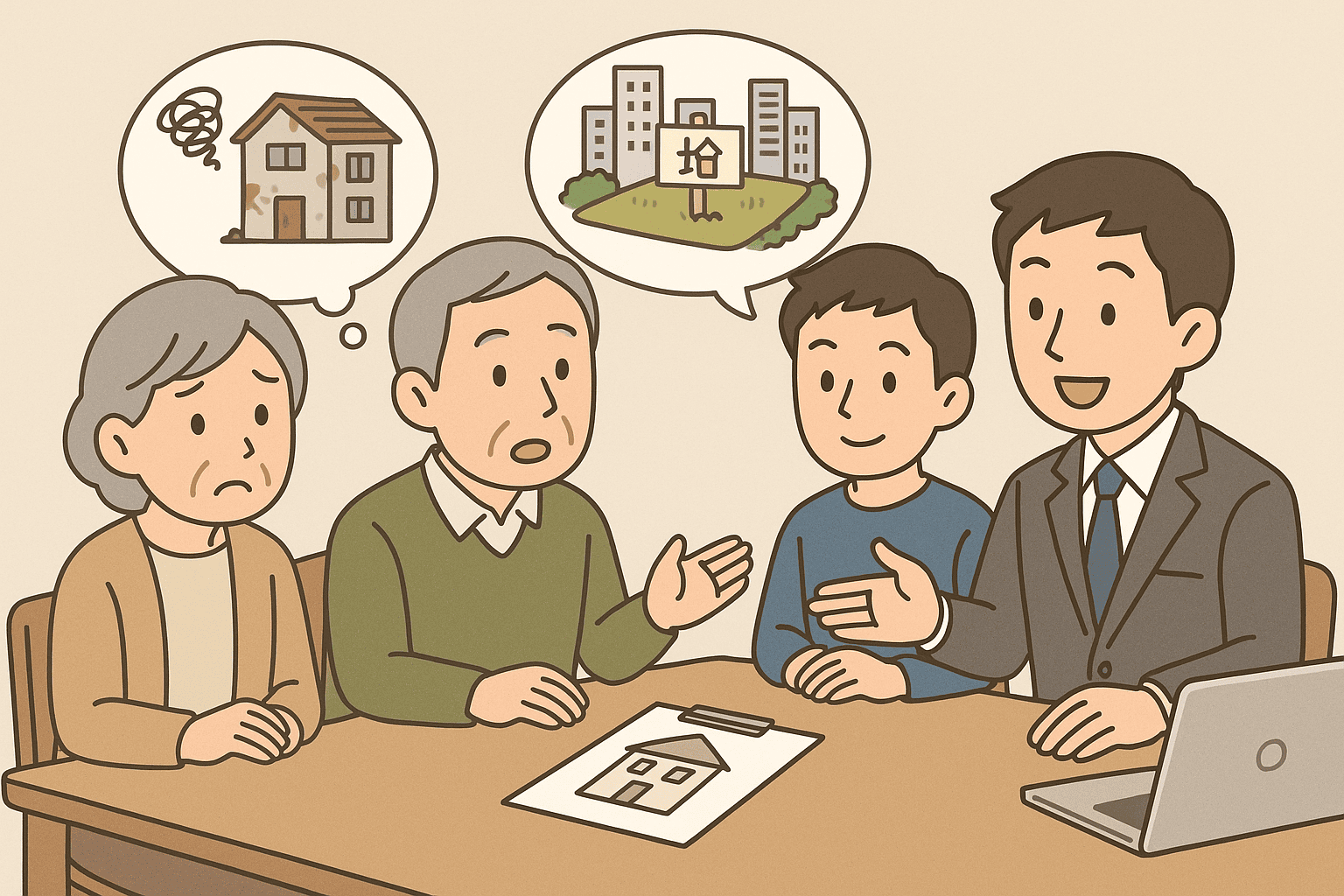
紹介したトラブルは、「情報の不足」と「感情のすれ違い」から生まれることが多いです。できるだけ早い段階で準備と対話をしておくことが、円満な相続への第一歩になります。
まとめ:“争続”を防ぐカギは、早めの準備と家族の対話
実家の相続は、法律だけでは割り切れない「感情」が大きく関わるテーマです。
誰が相続するのか、どう分けるのかを曖昧なままにしておくと、兄弟姉妹間でトラブルが起きやすくなってしまいます。
トラブルを防ぐためには、
・ 相続の基本ルールを正しく知ること
・ 実家の価値や分け方を具体的に話し合っておくこと
・ そして何より、家族の対話を大切にすること
「まだ先の話」と思わずに、親が元気なうちから準備を始めておくことで、大切な実家と家族の絆を守ることができるはずです。
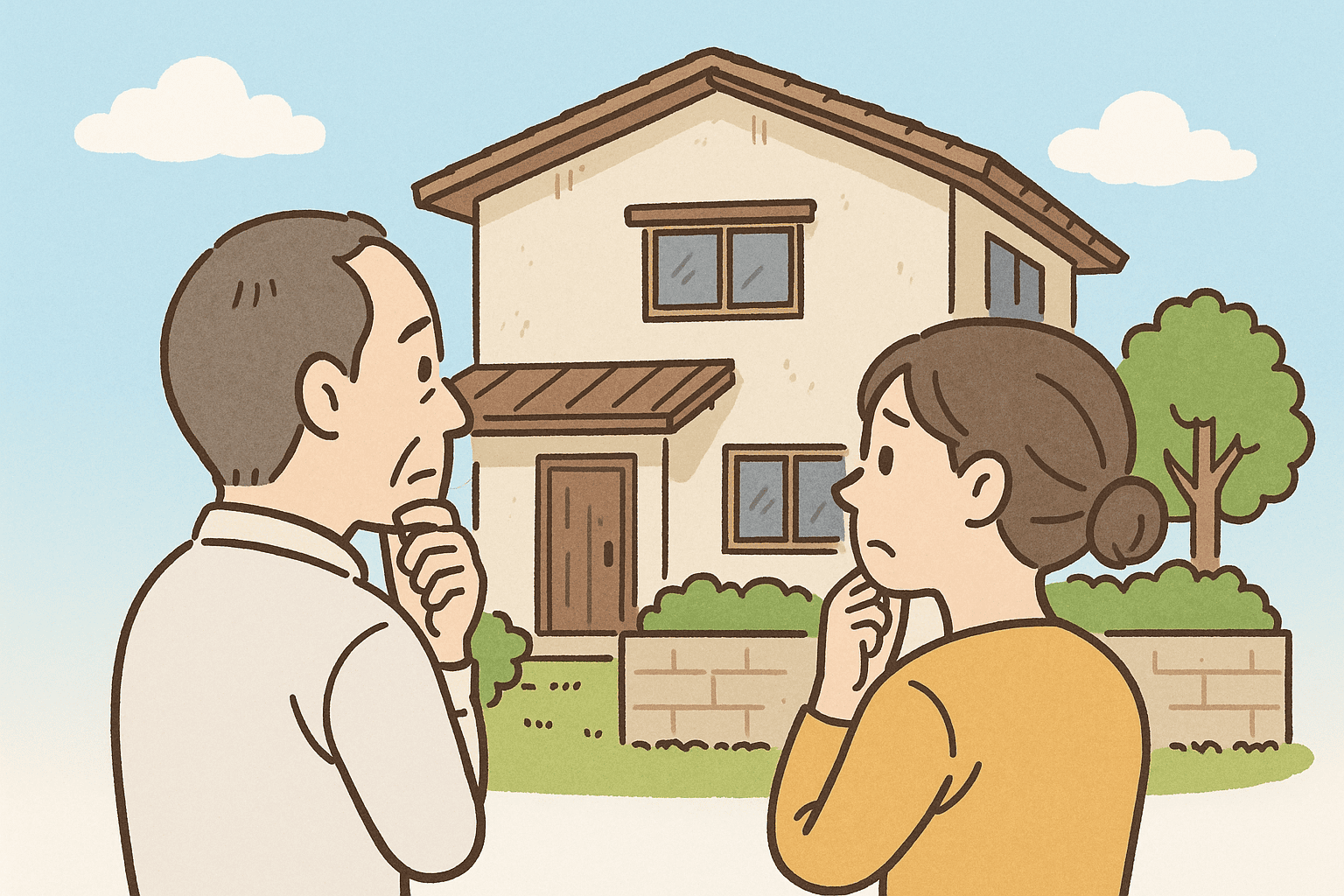
まずはお気軽にご相談ください。
今の実家の価値を知ることから始めませんか?
「うちはまだ大丈夫」と思っていても、
いざ相続が発生すると、
想像以上に話し合いが難航するケースも少なくありません。
まずは一歩踏み出して、実家の評価額を知っておくことが、家族の安心につながります。

